不動産鑑定士は今後なくなる?!将来性と業界の実態について
このページにはPR広告を含みます
- 「転職鉄板ガイド」ではPR広告を掲載しております。但し、報酬目的で虚偽の情報を発信したり、事実に反して優遇するなど、ユーザーの皆様にとって不利益になることは一切いたしません。
- 「転職鉄板ガイド」は皆様に有益な情報を提供するため、各公式HPやSNSなどからお客様の声を掲載することがあります。但し、あくまで個人的な感想のため、サービス内容を保証するものではありません。
- その他、個人情報の取り扱いや免責事項に関してはプライバシーポリシーをご確認ください。
 不動産鑑定士は、弁護士、公認会計士と並んで「日本の文系三大国家資格」と言われています。
不動産鑑定士は、弁護士、公認会計士と並んで「日本の文系三大国家資格」と言われています。
その割に、弁護士や公認会計士と比べて知名度は低く、「聞いたことがない」という方も居るでしょう。
不動産鑑定士とはどんな資格なのでしょうか。
「文系三大国家資格」と言われるくらいなんだから、弁護士や公認会計士のように安定した資格なのでしょうか。
ここでは、不動産鑑定士は将来性があるのか、取得したらどんな仕事をするのか、キャリアプランも含めて業界の実態を探ってみます。
不動産鑑定士とはどんな仕事なのか
不動産鑑定士は合格率5%の超難関資格
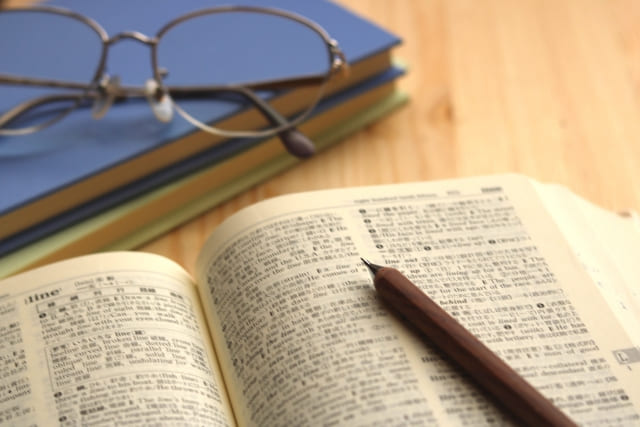 不動産鑑定士は名前の通り、不動産の鑑定を行う仕事です。
不動産鑑定士は名前の通り、不動産の鑑定を行う仕事です。
国家資格であり、この資格を持っていなければ不動産の鑑定はできません。つまり、独占業務となります。
不動産鑑定士が行った鑑定の結果は、国や地方自治体の公的な土地価格の指針になったり、融資の際の担保評価に用いられたりする、とても重要な役割を担います。
不動産の取引や、不動産投資は無くなることはないと言われます。したがって、独占業務であるだけに不動産鑑定士の仕事も常にあり、取得すれば「手に職」となることは間違いないでしょう。
しかし、同じ文系三大国家資格である弁護士や公認会計士のように、合格率は5%と大変低い数字です。
また取得までに数年かかるため、最近では受験者数も令和4年で871名(*)と、司法試験、公認会計士試験に比べて伸び悩んでいる現状もあります。
*参照:国土交通省『報道発表資料』
不動産鑑定士の仕事内容
 不動産鑑定士の仕事内容は、大きく分けると『不動産鑑定評価』と『コンサルティング業務』に分けることができます。
不動産鑑定士の仕事内容は、大きく分けると『不動産鑑定評価』と『コンサルティング業務』に分けることができます。
『不動産鑑定評価』は、国や地方自治体などの公的機関や、銀行や証券会社などの金融機関、不動産屋などの企業、投資家といったクライアントからの依頼によって、該当する不動産物件の鑑定を行います。
『コンサルティング業務』は、該当する不動産物件の立地や環境、交通機関や建物の構造などから、どのような需要があるかを探り、クライアントである不動産オーナーにどのような活用方法があるかといったコンサルティングを行う業務です。
業務フローとしては大まかに以下のようになります。
- クライアントから鑑定、またはコンサルティングの依頼を受ける
- 法務局や区市町村などの各役所から『登記情報』『固定資産評価証明』などの公的な物件情報を取得
- 現地でフィールドワーク
- 収集した情報を元に不動産価格を算定
- 『不動産鑑定評価書』を作成
- 作成書類をクライアントに提出し、適宜説明やプレゼンなどを行う
- クライアントからOKが出れば業務終了
クライアントは当然のことながら、損はしたくないし、できる限りの利益を得たいと考えます。
しかし不動産鑑定士はクライアントの損得に関係なく、正当な不動産価値を算出する義務があるため、衝突することも少なくありません。
クライアントが納得できるようにプレゼンを行う能力も求められる仕事だと言えるでしょう。
不動産鑑定士に将来性はあるのか?ないのか?
仕事は地方よりも都市部で探すほうが◎

残念ながら、地方の不動産鑑定士の仕事は年々減少傾向にあります。
地方ではどんどん人口が減っており、不動産物件の動きが鈍くなっているのが現状だからです。
そのため、不動産鑑定士の仕事はほぼ公的機関からの依頼に頼っている面が多いという声も聞きます。
また、不動産鑑定士は経験がものをいう業界でもあるので、若手の新規参入も難しい側面があるようです。
したがって地方で仕事を探すのはかなり難しくなっています。「不動産鑑定士はやめとけ」という否定的な意見を聞くのは、そういった理由からです。
将来性を考えるのなら、やはり都市部や首都圏で仕事を探すほうが良いでしょう。
昨今では不動産投資も注目されてきています。現代のニーズに合わせて就職先を選ぶことが大切です。
不動産鑑定のみでは停滞しがち。更に先を見据えるべき
 近年、「不動産鑑定はAIでもできるのではないか」、「不動産鑑定士はいらなくなる?」といった声が聞かれます。
近年、「不動産鑑定はAIでもできるのではないか」、「不動産鑑定士はいらなくなる?」といった声が聞かれます。
確かに、土地の規模、立地や交通、年齢別のニーズなど様々な情報をデータベース化してしまえば、基本的な不動産価値はAIでも十分算出可能ではあるでしょう。
しかし、時代やニーズの移り変わりはそう単純なものではありません。
ショッピングモールやアミューズメントパーク、宿泊施設と行った娯楽施設のニーズは、時代と共にコロコロと移り変わります。
そのため、コンサルタント業務に関して言えば、人間の感性に頼るほうがいい場面が多くありそうです。
一方で、公的機関や融資関連といった不動産鑑定は、今後AIが担うこともあるかもしれません。
だからこそ、不動産鑑定の範囲のみで凝り固まらず、その先を見据えて業務の幅を広げていくことが重要です。
バイタリティを発揮すれば、どこまでも将来の伸び率はあるのではないでしょうか。
不動産鑑定士に向いている人
 不動産鑑定は独占業務であるだけに、どんな業務が行われているのかよく分からない方も多いでしょう。
不動産鑑定は独占業務であるだけに、どんな業務が行われているのかよく分からない方も多いでしょう。
業務が分かりづらいと、どんな方に向いている仕事なのかもよく分からず不安に思う方もいらっしゃると思います。というわけで、どんな方に向いている職種なのか確認してみましょう。
不動産鑑定士に向いている方は、こんな方です。
論理的思考ができる
不動産鑑定士は、不動産物件の立地・周辺環境・交通の便や建物の利用価値・時代のニーズなど様々な条件を加味して鑑定を行います。
どのような条件で鑑定を行ったか、最終的に『不動産鑑定評価書』という書類に起こし、クライアントが納得するように論理的に説明する必要があります。
責任感がある
不動産鑑定士が算定した不動産鑑定結果は、公的な不動産価格の指針になったり、金融機関の融資を行う際の担保評価に用いられたり、投資家の指標になったりと、国内の経済に大きく関わる仕事です。
正当な評価を行う義務があり、適当な心づもりで行える仕事ではありません。
客観的に物事が見れる
当然ですが、自分の好みなど、私情を挟むわけにはいきません。仕事を行う上では常に客観的な視点で不動産物件の詳細を確認して、正当な判断を行わなければなりません。
常に情報をアップデートできる
不動産価値は日々変動します。時代によって土地や建物の形状、利用方法、ニーズは刻一刻と変わります。
土地人気の流行り廃り、時代や世代によるニーズに敏感になれる人は楽しく情報もアップデートし、仕事に反映できるでしょう。
デスクワークとフィールドワークどちらも好き
文系三大国家資格と呼ばれるだけあり、デスクワークも多い仕事ですが、そこに到るまでのフィールドワークも多い仕事です。不動産鑑定士を経験している方の「いいところ」には「あちこちに行ける」ことを上げる方も多いくらいです。
どちらかだけでは成り立たず、デスクワークもフィールドワークも両方好き!という方に向いています。
体力がある
上記でも言ったように、フィールドワークがかなり多い仕事です。不動産物件によっては山林に赴いたり、地方の原野などに遠出しなければならないことも多いので、体力は必須です。
細かいことが気になる
何度も上げていますが、不動産鑑定はあらゆる要因を加味して不動産価値を算定するため、情報を漏らす事なく細かい作業ができる方に向いています。
不動産鑑定士はどんなスキルが必要?
次は必要なスキルについて考えてみましょう。
コミュニケーション能力
クライアントとのやり取りだけでなく、フィールドワークに行った際には、近隣に住んでいる方への聞き込みを行うこともあります。
できるだけ多くの情報を聞き出したり、またクライアントとの認識の齟齬を埋めたりする必要もあるので、コミュニケーション能力は大事です。
プレゼン力
特にコンサルタント業務に携わりたい方には重要なスキルです。持っている情報や不動産をどの用に利用すれば利益を出すことができるかなど、クライアントに対して分かりやすく、かつ興味を持ってもらえるようにプレゼンする能力も重要です。
アイディア力
こちらも特にコンサルタント業務には必要スキルです。ありきたりの企画ではあなたに依頼した意味がないと思われても仕方ありません。土地柄や世代と時代、建物の様子を見て面白いと思ってもらえる企画を立てられるアイディア力は重宝します。
構成力
鑑定を行う際にどのような要因からこの算定を行ったのか、書類を作成する上でも、クライアントに説明する上でもしっかりと構成を行ったものは説得力があります。
不動産鑑定士はどんな就職先がある?
不動産鑑定士資格を取得したら、次は就職先です。不動産鑑定士は独占業務であるだけに、就職先には困らないと思います。
また難関資格で取得人数も少ないだけに、売り手市場な側面もあります。
不動産鑑定士の就職先は大きく分けて3つに分けることができます。
- 不動産業界
- 金融業界
- コンサルティング業界
不動産鑑定事務所・不動産会社など
信託銀行などの金融機関・証券会社・監査法人など
それぞれの業界で行う業務も変わってきます。自分がどのような業界で、どのような業務を行いたいか。またどのように活躍したいか。キャリアパスなども踏まえて選ぶといいでしょう。
不動産鑑定士になるには?試験と実務の注意点
試験合格と実務経験が必要な長期戦
不動産鑑定士になるには、まず当然のことながら『不動産鑑定士試験』を受験しなければなりません。
資格取得までを分かりやすくフロー化すると以下のようになります。
- 短答式試験に合格
- 論文式試験に合格
- 国土交通大臣の登録を受けた機関で実務研修(1年コースor2年コースを選択)
- 国土交通大臣の修了考査
- 国土交通大臣の修了確認・不動産鑑定士として登録
このように、試験だけでも難関なのに、更に1~2年の研修期間も必須となります。
研修期間は先輩について実地研修を行いながら、eラーニングなどで必要な単位を取得する形式となります。
1年コースは早く短く取得できる分、スケジュールがかなりタイトになるため、2年コースでじっくり学ぶ方が一般的です。
*参照:国土交通省『実務修習』
研修期間は経済的に困窮しやすい
不動産鑑定士試験は最難関試験と言われるだけあり、片手間に勉強して取得できる資格ではありません。不動産鑑定士資格を取得するために、仕事を辞めて試験勉強に専念するという人も居るほどです。
独学は限度があるため、教育機関や通信教育を受講するのが良いとされますが、当然受講料がかかります。
さらには、いざ試験に合格しても『研修生』として1~2年の実地研修があります。
研修生は薄給で働くことになりやすく、この時点で経済的に悲鳴を上げてしまうパターンも少なくありません。
不動産鑑定士を目指す際には、できる限り経済的な準備をしておくことも必要になります。
不動産鑑定士との併用で有利になる資格
 不動産鑑定士資格は国家資格ではありますが、一方で独立がしづらいとも言われます。
不動産鑑定士資格は国家資格ではありますが、一方で独立がしづらいとも言われます。
経験がものをいい、年齢が高くても引退せずに長く続けられる職種になりますので、世代交代がなく、若い世代が新規に仕事を取りづらいという面があるのです。
上の世代と同様の仕事をしていてはなかなか仕事に恵まれないという声も多く聞かれます。
そのため、例えば他の資格と併用して新しい仕事の仕方を確立したり、営業力を身に着けコンサルト業に力を入れるなど、工夫が必要な時代かもしれません。
不動産鑑定士と併用して利用できる資格は下記のものがあります。
- 宅地建物取引士
- 土地家屋調査士
- 公認会計士
「不動産鑑定士ですらやっと取ったのに、これ以上取るのは…」という方もいるでしょう。
現実的に無理だと思う方は、例えばこれらの資格を持っている人と合同で開業し、分業するといった手もあるので、検討してみるのもいいかもしれません。
【まとめ】不動産鑑定はAIでも可能!?不動産鑑定士はなくなるか
 以上、不動産鑑定士の現状を少々厳しい視点も含めて見ていきましたが、いかがだったでしょうか。
以上、不動産鑑定士の現状を少々厳しい視点も含めて見ていきましたが、いかがだったでしょうか。
実際にAIで対応できるところもあるのでしょうが、とはいえすべてがAIでまかなえるかというと、そうではないはずです。
不動産鑑定士は国家資格であり、独占業務でもあるので、きっとなくなることはないでしょう。
将来性を考えるのなら、これからの若い世代が新しい不動産鑑定士の仕事の仕方を考える時代に入っているのかもしれませんね。
不動産鑑定士を活かせる求人を探すなら『doda』
 1つのサイトで求人検索とエージェントのサービスが受けられるdoda。
1つのサイトで求人検索とエージェントのサービスが受けられるdoda。
実務を積みつつ、働きながらの資格取得を目指す方の利用もおすすめです。
一度登録してみて、求人検索、転職アドバイスをもらうのも有効です。