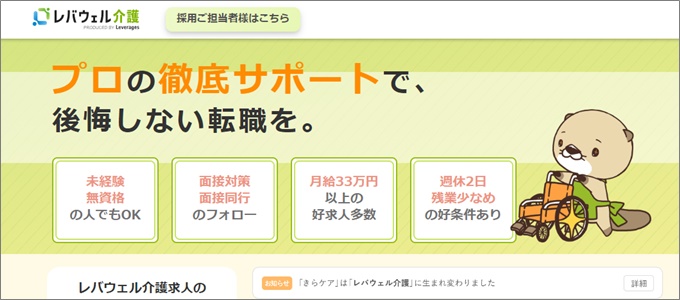福祉ネイリスト資格とは?取得にかかる費用と求人の見つけ方
このページにはPR広告を含みます
- 「転職鉄板ガイド」ではPR広告を掲載しております。但し、報酬目的で虚偽の情報を発信したり、事実に反して優遇するなど、ユーザーの皆様にとって不利益になることは一切いたしません。
- 「転職鉄板ガイド」は皆様に有益な情報を提供するため、各公式HPやSNSなどからお客様の声を掲載することがあります。但し、あくまで個人的な感想のため、サービス内容を保証するものではありません。
- その他、個人情報の取り扱いや免責事項に関してはプライバシーポリシーをご確認ください。

近年、注目されて人気が出ている福祉ネイリストの資格。
「いくつになっても爪がきれいだと嬉しい」と、高齢者施設や福祉施設の利用者の間でネイルアートの需要が増えているのです。
今回は、福祉ネイリストになるために必要な費用や、求人の探し方を紹介します。
福祉ネイリストとは
福祉ネイリストとは、高齢者や障がい者、災害による被災者など心にダメージを負った方に対し、ネイルによって癒しや喜びを与える専門的なネイリストのことです。
一般的なネイリストは、お店に常駐しお客様に来店してもらうのが通常です。
一方、福祉ネイリストにとってのお客様は、ネイルサロンに自分で行くことが難しい高齢者や障害者の人です。
そのため福祉ネイリストは、高齢者施設や障害者施設に赴いたり、時には自宅に訪問することもあります。
福祉ネイリスト資格をとるには
福祉ネイリストの資格は、JHWN(一般社団法人 日本保健福祉ネイリスト協会)が主催する福祉ネイリスト認定制度を受ける必要があります。
福祉ネイリスト認定制度のステップ
福祉ネイリスト認定制度のステップは以下の通りです。
- 認定校にて21時間の講習(3時間の講習×7日間のカリキュラム+宿題)
- 実施研修3時間(講師同行+レポート提出)の講習
- 卒業試験
合格者は、講師と共に実地研修を行い、ディプロマという認定書を発行してもらったところで晴れて福祉ネイリストに認定されます。
福祉ネイリスト資格を得るための費用
費用は講習費88,000円、登録料3000円の他、材料費が別途必要となるようです。
なお、JNECネイリスト技能検定2級以上の取得者であれば、講習費が44,000円となり、実技の一部も免除されます。
福祉ネイリスト資格はこんな人におすすめ!
福祉ネイリストの資格がおすすめなのはこのような人たちです。
福祉ネイリスト資格はこんな人におすすめ
- 現在ネイリストとして働いている人
- 現在福祉施設で働いている人
なぜおすすめなのかを紹介します。
現在ネイリストとして働いている人
 現在ネイリストとして働いている人の中には、「年齢を重ねてもネイリストは通用するのだろうか?」という不安を持っている人もいるでしょう。
現在ネイリストとして働いている人の中には、「年齢を重ねてもネイリストは通用するのだろうか?」という不安を持っている人もいるでしょう。
ネイルを好むお客様は若い人がメインです。「昔はネイルサロンによく行っていたけど、子どもが生まれてネイルができなくなった」という人も多くなります。
中高年の女性の中にもネイルサロンに通う人はいますが、主に若い人を施術するにあたり、求められるのは若い感性やセンスを持った同年代の施術師でしょう。
そのため、ネイリストとして歳を重ねていくことに迷いが出るのは当然です。
その点福祉ネイリストは、お客様が高齢者であることが多いので、今まで通りの自分のセンスを信じて良いのです。
超高齢化社会が進む中で、福祉ネイリストの需要はどんどん高まっています。
福祉ネイリスト資格を取得すれば、ネイリストのセカンドキャリアとして、新しく道を切り開くことができるでしょう。
また、もしあなたがすでにJNECネイリスト技能検定2級以上を取得しているなら、福祉ネイリストの講習費は半額の44,000円となり、実技の一部も免除されます。
JNECネイリスト2級を持っているなら、福祉ネイリストを取得して損はありません。
福祉ネイリストは、ネイリストのセカンドキャリアとしてもおすすめ!
現在福祉施設で働いている人
 現在、介護施設や障害者施設で働いている人にも、福祉ネイリスト資格の取得はおすすめです。
現在、介護施設や障害者施設で働いている人にも、福祉ネイリスト資格の取得はおすすめです。
なぜなら、施設内で貴重な人材になれるからです。
福祉施設側が、施設利用者にネイルを提供したいと考えたとき、通常はネイリストの人に施設まで来てもらうという手配をしなければなりません。
一方、もし施設内に福祉ネイリストの資格を持つ職員がいたらどうでしょうか。ネイリストを派遣してもらう手間や費用もかかりません。福祉施設にとってとても重宝される人材となれるのです。
これは転職の際にも有利です。福祉施設の中には、ブラックな職場も少なくありません。
福祉ネイリスト資格と介護・福祉資格の両方を持つ人材は貴重なため、よりホワイトな職場への転職も可能になりますよ。
福祉ネイリストは、介護職員のダブルライセンス資格としてもおすすめ!
福祉ネイリストが福祉施設で働くには?ホワイト求人の探し方
「福祉ネイリストを求めている施設ってどこにあるの?」と思う人も多いでしょう。
人手不足の介護・福祉業界では、求人の数は山ほどあります。その中から、一人で自分に合った職場を探し出すのはとても難しいでしょう。
そのため、介護の転職のプロに相談するのが一番の近道です。中でもおすすめなのは、「レバウェル介護」の利用です。
「福祉ネイリストを取得して職場を変えたい」「少しでもいい施設に転職したい」と思ったら、一度レバウェル介護に登録してみてください。
「今までネイリストだったから介護の資格なんて持ってないんだけど…」という人でも大丈夫。レバウェル介護には、介護職未経験OK・無資格OKの求人がたくさんあります。
登録すると専門のアドバイザーが担当につき、転職の相談に乗りながら求人を探してくれます。
「福祉ネイリストの資格を取った(またはこれから取ろうと思っている)」ということを伝えれば、ぴったりの求人を紹介してくれるはずです。
| 公式サイト | https://job.kiracare.jp/ |
|---|---|
| おすすめポイント | アドバイザーの丁寧な対応が評判 |
【まとめ】福祉ネイリスト資格で新たな道を切り開こう
ネイリストのセカンドキャリアとしても、介護職員のダブルライセンスとしてもおすすめの福祉ネイリスト資格。
これから超高齢化社会になるにつれ、需要が高まっていく職業であることは間違いありません。
ぜひ資格を取得して、これからの将来に繋げてください。