独学で消費生活アドバイザーに挑戦|難易度や勉強方法、おすすめのテキストを紹介
このページにはPR広告を含みます
- 「転職鉄板ガイド」ではPR広告を掲載しております。但し、報酬目的で虚偽の情報を発信したり、事実に反して優遇するなど、ユーザーの皆様にとって不利益になることは一切いたしません。
- 「転職鉄板ガイド」は皆様に有益な情報を提供するため、各公式HPやSNSなどからお客様の声を掲載することがあります。但し、あくまで個人的な感想のため、サービス内容を保証するものではありません。
- その他、個人情報の取り扱いや免責事項に関してはプライバシーポリシーをご確認ください。
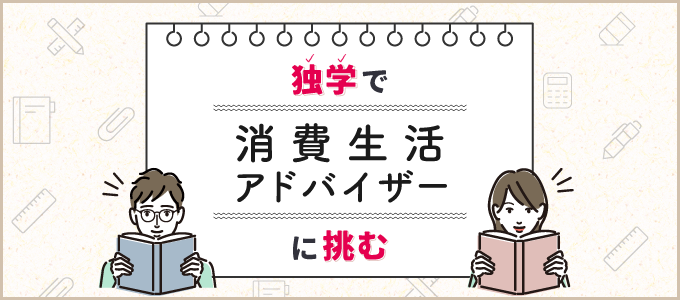
 消費生活アドバイザーは、企業の消費者対応部門や公的機関の消費者相談窓口で活かすことができる資格です。
消費生活アドバイザーは、企業の消費者対応部門や公的機関の消費者相談窓口で活かすことができる資格です。
資格試験の合格率は、20%台から30%台に上昇してきています。また2021年度においては1次試験に新しくCBT試験が導入され、2次試験の出題数も減りました。このような背景から消費生活アドバイザーの試験は、年々受験しやすくなっているといえます。
一方で試験範囲の広さ、参考書籍・問題集が一般に流通しづらいことなど、独学での勉強が難しい面もあります。
この記事では、消費生活アドバイザー資格試験の難易度、受験のための勉強方法やおすすめのテキスト、受験対策ができる通信講座について調査した結果を紹介しています。独学で合格を目指す人はもちろん、どのような通信講座があるのか知りたい人も参考にしてみてください。
消費生活アドバイザーとは
消費生活アドバイザーとは、簡単に言えば商品を提供する企業と商品を購入する顧客の間の橋渡しをする存在です。
消費生活アドバイザーには、以下のような役割があります。
- 顧客の意見を企業や行政に届ける
- 顧客の苦情相談になどに適切なアドバイスをする
 消費生活アドバイザーは、企業においては販売戦略、広報、商品開発、消費者対応、コンプライアンス部門など幅広い分野での活躍が期待できます。また苦情に対する相談相手という立場として、公的機関の相談受付業務に係ることもできます。
消費生活アドバイザーは、企業においては販売戦略、広報、商品開発、消費者対応、コンプライアンス部門など幅広い分野での活躍が期待できます。また苦情に対する相談相手という立場として、公的機関の相談受付業務に係ることもできます。
なお消費生活アドバイザー試験は、消費生活相談員資格試験を兼ねています。1つの試験に合格すれば、消費生活アドバイザーと消費生活相談員の2つの資格を得ることができるのです。
消費生活相談員は国家資格であり、国民生活センターや消費生活センターなどで働くときに活かすことが可能です。
※消費生活アドバイザーの資格取得のためには、合格後登録申請が必要です。
受験資格
- 特になし
受験料
- 16,500円
1次試験免除者(前年度1次試験に合格しており、今年度は2次試験のみ受験する場合)は
13,200円
※合格の際は受験料とは別に消費生活アドバイザー登録管理手数料11,000円が必要
受験日程(2023年度)
- 1次試験
- 2次試験
10月14,15,21,22日から選択(14,22日は13:30~15:30、15,21日は10:00~12:00)
12月10日
試験方式
- 1次試験
- 2次試験
選択式(会場でコンピューターを利用して解答するCBT試験)
論文と面接
試験内容と試験時間
- 1次試験全30問(120分)
- 2次試験 論文試験(60分)+面接試験(10分)
消費者問題
消費者行政・法律知識
経済・企業経営の一般知識
生活基礎知識
論文試験(消費者問題、法律知識、企業経営の一般知識の3題から1題を選択)
面接試験
合格基準(2022年度試験)
- 1次試験
- 2次試験
正解率65%以上
- 論文試験
- 面接試験(面接免除制度有り)
消費生活アドバイザー及び消費生活相談員として必要な、出題の理解力、課題の捉え方、表現力等を審査し、選択した2題それぞれが5段階評価(A~E)のC以上を合格とする。
消費生活アドバイザー及び消費生活相談員として必要な、見識、相応しい態度、積極性、コミュニケーション能力等について審査し、面接委員の総合評価が3段階評価(A~C)のB以上を合格とする。
合格基準引用元:一般社団法人日本産業協会『消費生活アドバイザー試験』
有効期限
5年
消費生活アドバイザー資格試験の難易度考察
合格率からの難易度考察
 消費生活アドバイザー資格試験の2022年度合格率は、30.0%となっています。その前年2021年度試験の合格率は31.2%となっており、近年の合格率は30%台を推移していることが分かります。
消費生活アドバイザー資格試験の2022年度合格率は、30.0%となっています。その前年2021年度試験の合格率は31.2%となっており、近年の合格率は30%台を推移していることが分かります。
2017年度以前は大体20%前半の合格率が続いていたため、消費生活アドバイザー資格試験の合格率は徐々に高くなっていると考えられます。
また、2次試験には論文試験、面接試験と知識の暗記だけでは対策できない試験形式が並んでいますが、1次試験に比べて2次試験の合格率は高い傾向にあります。例えば、2022年度試験において1次試験の合格率は約36.9%、2次試験の合格率は70.3%となっています。
合格率引用元:一般社団法人日本産業協会『消費生活アドバイザー試験』
また、消費生活アドバイザー資格試験では、1次試験に合格すると翌年度まで1次試験が免除になるという制度があります。この制度を利用すれば受験料はかさむものの、2年かけて合格を目指すという学習プランを立てることもできるでしょう。
試験方式の変更から考える難易度の変化
2021年度の試験からは試験の仕組みが新しくなり、より受験しやすい内容に変わりました。3つの変更点を見てみましょう。
1つ目は、1次試験にCBT試験というコンピューター方式の試験が導入されたことです。これにより、全国47都市のテストセンターで受験が可能になりました。2020年度は日本全国わずか9都市でしか受験できなかった消費生活アドバイザー資格試験の間口が、一気に広がったといえます(ただし、2次試験に関しては5都市でしか受験できません)。
2つ目は試験日程の増加です。以前は1日しかなかった受験日程が4日程に分かれたことで都合が良い日付と時間を選びやすくなりました。
3つ目は、論文試験の出題数減少です。2次の論文試験では従来2題が出題されていましたが、2021年度からは1題に変更されました。これにより、試験時間も120分から60分に短縮されています。
これらの新しい試験体制により、消費生活アドバイザー資格試験の難易度はまた少し低くなると考えることができるでしょう。
総合的な難易度は普通レベルだが、油断は禁物
 消費生活アドバイザーの合格率は、資格試験としてはそこまで高くないといえるでしょう。また、近年は合格率が上昇気味であり、新試験制度によって試験が受けやすくなっています。
消費生活アドバイザーの合格率は、資格試験としてはそこまで高くないといえるでしょう。また、近年は合格率が上昇気味であり、新試験制度によって試験が受けやすくなっています。
ただし、消費生活アドバイザーは試験範囲が非常に広いという特徴もあります。合格率だけをみて「それほど難しくないだろう」と考えてしまうのは危険です。
消費生活アドバイザー試験の勉強時間
 消費生活アドバイザー資格試験に必要な勉強時間は、事前に受験者が持っている知識にも左右されるので一概には言えません。
消費生活アドバイザー資格試験に必要な勉強時間は、事前に受験者が持っている知識にも左右されるので一概には言えません。
大体3~7ヶ月程度、時間にして500~600時間前後といわれていますが、その半分以下の勉強時間で合格している人もいるようです。
一方で試験内容を甘く見積もりすぎ、数年越しの勉強になった受験生も存在します。
まずは公式ページで閲覧できる過去問とテキストの内容などに目を通し、自分に必要な勉強時間を図るようにしてみてください。
消費生活アドバイザー資格試験は独学可能か
消費生活アドバイザー資格試験は独学可能か調査すると、独学で合格している人もいる一方、途中で挫折している人も見られるという結果になりました。
生活に身近な試験内容であると考え、テキストを読んでみたら試験範囲の広さに愕然としてしまったという受験者もいるようです。
最初にテキストや過去問集で試験内容をざっと見渡してみて、自分が独学で挑めるかどうかを判断することが大事でしょう。
受験料と教材費が他の資格試験に比べ比較的高いこと、合格後も5年後には更新費用が掛かることを考えればできるだけ効率よく勉強したいところです。
消費生活アドバイザー対策ができる通信講座もありますので、独学に限界を感じた場合はこれら講座を利用することを検討してみてください。
消費生活アドバイザーの具体的な勉強方法
基本的な勉強方法はテキストで知識をインプットし、過去問で実践演習を積むという形です。
 参考書は分厚いので、一度目ですべて頭に入れようとしないで大丈夫です。最初はざっと読み、2周、3周と繰り返す中で内容が理解できるようにしていきます。まとめノートを作る、テキストに書き込むなど理解を進めるための自分なりの工夫をしてみてください。
参考書は分厚いので、一度目ですべて頭に入れようとしないで大丈夫です。最初はざっと読み、2周、3周と繰り返す中で内容が理解できるようにしていきます。まとめノートを作る、テキストに書き込むなど理解を進めるための自分なりの工夫をしてみてください。
また、1ページ目から順番に読もうとせず、自分にとってなじみがあるところからつまみ読みしていくのもOKです。
テキストの内容がある程度頭に入ってきたら、過去問を解いていきます。
なお、過去問に早めに取り組んで試験に出る部分を絞り込んでから、インプットを行うという勉強方法もあります。
試験範囲が膨大でインプット作業にやる気が出ない場合は、先に過去問を解いてみても良いでしょう。
過去問は1度やったら終わりではありません。数年分を繰り返し解いて、内容を身に着けていきます。過去問を解くことで苦手分野が浮き彫りになってくるはずです。過去問のポイントは暗記カードやノートなどにまとめて、後々集中的に振り返えられるようにしておくと良いでしょう。
なお、消費生活アドバイザー資格試験対策として時事問題に関するアンテナを貼っておく必要もあります。1次試験、論文試験、そして面接でも時事問題が関連してくる可能性があるからです。新聞を読む習慣をつける、試験年度中の法改正情報に気を付けるなどの対策をしておきましょう。
2次試験対策には1次試験が終わったころから取り組む人が多いようですが、時間が足りないという声も聞かれます。できれば1次試験の勉強後半ぐらいから取り組みたいところです。
小論文の勉強方法は、とにかく実際に書いてみることです。小論文の基本構成(序論→本論→結論)を意識して過去の小論文問題を解いてみてください。よく出題される問題が分かったら、あらかじめどのように書くかを決めてしまうと本番で構成を考える時間が短縮されます。
面接試験については、あらかじめ聞かれそうな問題の答えをシュミレーションしておくとよいでしょう。質問例としては、以下のようなものがあげられます。
- 資格取得の動機
- 資格取得したらどのように生活や仕事に活かしていくのか
- 資格取得のための勉強方法
- 今の仕事について
- 最近気になったニュース
試験対策に使えるおすすめの教材や通信講座
 消費生活アドバイザーの資格試験をする上で、ネックになるのが市販参考書の少なさといえるでしょう。社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーなどの試験では多くの資格試験対策教材が書店やオンラインショップ内で見つかるはずです。
消費生活アドバイザーの資格試験をする上で、ネックになるのが市販参考書の少なさといえるでしょう。社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーなどの試験では多くの資格試験対策教材が書店やオンラインショップ内で見つかるはずです。
一方消費生活アドバイザーの試験に関しては、参考書・問題集が一般の書店で流通していない場合があります。
独学で受かるためには、消費生活アドバイザー資格試験対策の教材を自力で手に入れる必要があります。この項では受験対策に使える参考書・問題集の特徴および(2023年7月現在における)入手方法を紹介していきます。
過去問は公式ページで公開されている
実は2020年度以降の過去問については、以下の公式ページで無料公開されています。
1次試験、2次試験の問題と、1次試験の正答はこのページから閲覧することができます。これを見れば勉強を始める前に、試験全体の雰囲気を掴むことができるでしょう。
ただし正答と言っても解説はついていません。過去問を詳しく研究したいという人は、別途過去問集を購入することを検討してみてください。
参考書・問題集・教材等のおすすめテキストの特徴と入手方法
消費生活アドバイザー資格試験 公式テキスト
消費生活アドバイザー資格試験を実施している日本産業協会の公式テキストです。
試験内容の多くはテキストに準拠して出題されますので、独学でのインプット用教材としては頼れる存在と言えるでしょう。
毎年法令の改定等に合わせて内容が変更されているので、購入の際は受験年度にあったものを買うようにしましょう。
4冊分冊式で発売されており、1冊あたり大体200~250ページ前後です。1冊で3,300円、4冊フルセットで9,900円になります。
消費生活アドバイザー資格試験公式ページの「試験対策」(以下URL)から購入画面に移行できます。
一般的な書店や他のインターネットショッピングサイトには流通していません。
http://www.nissankyo.or.jp/adviser/examination/shiken-taisaku.html
徹底解説 消費生活アドバイザー試験問題全解説
消費生活アドバイザー試験問題を詳しく解説している過去問題集です。重要用語集や関連年表などの特典も充実しています。
価格は1年度分の過去問で3,980 円(税込み)となっています。
独学で受かるためには過去問を手に入れることは大事ですので無料過去問もありますが、テキストで勉強したい方には4,000円未満で購入できるのでお勧めです。
産業能率大学総合研究所のホームページで、「能産大の通信講座」→「書籍・問題集一覧」から購入できます。
また、Amazon等ネット書店で販売されていることもあります。
https://sannopub.com/item-detail/842768
消費生活アドバイザー受験合格対策
消費生活アドバイザーの膨大な試験範囲が1冊にまとまっている受験対策本です。
出題傾向の分析、分野別解説、過去問で構成されており、2次試験対策まで可能です。執筆陣はすべて消費生活アドバイザー有資格者です。
ページ数は2021年度版で611ページと非常に分厚いですが、公式テキスト5冊分の総ページ数と比べれば、コンパクトにまとまっている方ではないでしょうか。
価格も7,150円と一見高く感じますが、公式テキストと比較すれば約半額になります。
一般の書店で流通しています。Amazon他、一般書店でも入手できます。
くらしの豆知識
「くらしの豆知識」は国民生活センターが提供している消費者が知っておきたい知識をまとめた小冊子です。
消費者トラブルを回避するためのお金の知識や契約の基礎知識が図表、イラスト入りで解説されています。2次試験を含む消費生活アドバイザー資格試験全分野に対応できる一冊です。
全国の官報販売所で購入することができます。Amazonでも取り扱いがあります。
観光販売所一覧:https://www.gov-book.or.jp/portal/shop/
冊子版だけでなく電子書籍版も発売されています。以下のURLから購入可能な電子書店が閲覧できます。
http://www.kokusen.go.jp/book/data/e-book.html
ハンドブック消費者
消費生活に関する各種法令や制度について解説している本です。消費者政策の現状等についてもまとめてあります。
「ハンドブック消費者」はいかにも「政府刊行物」といった内容になっています。
消費者庁のホームページで、全文無料で閲覧できます。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/handbook/
受験対策ができる通信講座
産業能率大学の通信講座
公式サイトでも紹介されている産業能率大学の通信講座で個人が申し込めるものには、総合コースと速習コースの2種類があります。
総合コースでは、公式テキストを使った1次試験対策(添削付)他、2次試験の小論文対策(講師による小論文添削1回付)が可能です。
速習コースでは、「消費生活アドバイザー受験合格対策」と「徹底解説・消費生活アドバイザー試験」、そして時事問題資料集と添削問題がセットになっています。1次試験対策に特化している講座と言えます。
これらの通信講座は、参考書や問題集がセットになっています。最初は独学を考えて参考書を購入したけれど後から通信講座を受講しようと思い直す、そういうこともあるでしょう。
しかしこの場合、教材が2重になってしまう可能性があるので注意してください。できれば、教材を購入する前に受講の検討をしておくと良いと思います。
資格の学校LEC
LECでは無料でガイダンス動画を配信している他、「出題予想問題集」の出版も行っています。
また、1次試験、2次試験別のスピード合格講座も実施予定です。現時点(2023年8月現在)では2023年度の通信講座詳細は発表されていますので、最新情報をチェックしてみてください。
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)試験対策講座
20年にわたる実績を持つ消費生活アドバイザー試験対策講座です。2021年度は新型コロナ対策のため、有料動画として対策講座を配信予定です。なお、無料の受験ガイダンス動画も公開されています。学習スタート前に、一度視聴してみてはいかがでしょうか。
まとめ 資格試験対策、独学が厳しければ通信講座の検討を
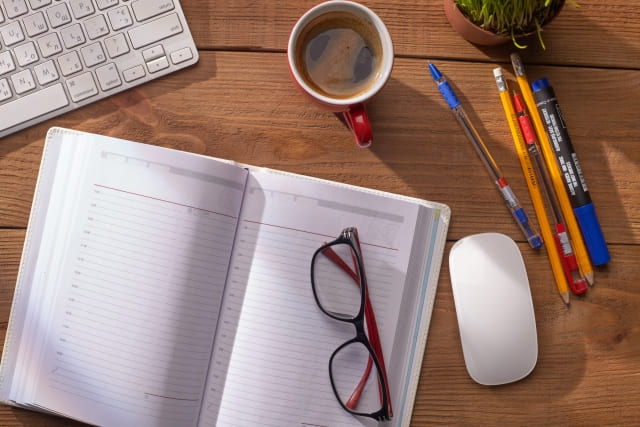 消費生活アドバイザーの合格率は近年30%台になっています。
消費生活アドバイザーの合格率は近年30%台になっています。
そこまで低い合格率ではありませんが、試験範囲の広さは甘く見ることができません。
また、1次試験と2次試験に分かれているため、1次試験の勉強に集中しすぎて2次試験の勉強が足りなかったという受験生の声も聞かれます。1次試験、2次試験ともに計画的な勉強を進めることが大事です。独学合格可能かどうか分からなければ、通信講座受講の検討をしてみてください。
試験勉強に使えるテキストや問題集は、一般書店だけでは集めきれないのもこの試験の特徴です。記事に記載した入手方法を手掛かりに、各種教材を購入しましょう。
なお産業能率大学の通信講座への申し込みを検討している人は、先に参考書等を準備すると教材が二重になってしまう可能性があります。通信講座付属の教材を確認の上、参考書等を購入してください。




